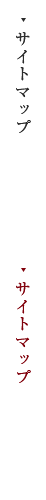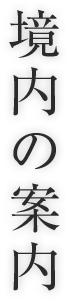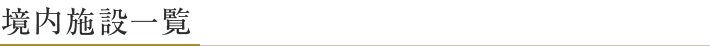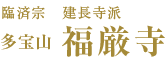本堂
福厳寺の創建については、今から八百年以上前、寿永元年(1182年)四月、足利又太郎忠綱の本願により建立されたとの説があります。
禅宗寺院となったのはその後のことで、南北朝時代・康永二年(1343年)に建長寺開山大覚禅師三世の法孫實堂権和尚を開山として迎え、以後六百五十年以上禅宗寺院として歴史を刻んできました。
本堂の歴史は福厳寺五世賢翁和尚の代(明応年間、1490年頃)再建された記録があります。
現在の本堂は文政十一年(1828年)に建てられたものです。明治二十五年(1892年)、二十四世玉潭龍和尚の頃、屋根の修理がなされましたが、その後の大正六年(1917年)に二十六世福山文應和尚により茅葺屋根から瓦葺屋根に改修された経緯があります。
そして平成八年に本堂裏土留め工事、屋根総替え、回廊、位牌堂増築の大改修を行い、翌年十月十九日に落慶法要を大本山建長寺吉田正道管長猊下導師の下で厳修致しました。
ご本尊は「釈迦牟尼如来」(お釈迦様)であり、檜材寄木造りの禅定印を結ぶ坐像です。室町時代十五世紀頃の院派系仏師の作と推定される仏像です。中世にさかのぼる点で貴重であり、平成九年に足利市重要文化財に指定されました。